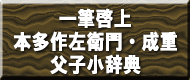 目 次 参考資料 |
HOME>(a)本多氏一族の系譜>(1)助時系
|
|
| (a)本多氏一族の系譜 (0)始祖 (1)助時系(直系) (2)正時系(伊奈本多) (3)正明系 (4)正経系(本多豊後守家)
|
||
| ▲ページトップへ戻る |
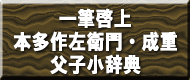 目 次 参考資料 |
HOME>(a)本多氏一族の系譜>(1)助時系
|
|
| (a)本多氏一族の系譜 (0)始祖 (1)助時系(直系) (2)正時系(伊奈本多) (3)正明系 (4)正経系(本多豊後守家)
|
||
| ▲ページトップへ戻る |