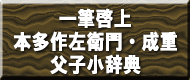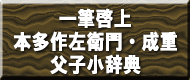(1)家康の背中のおでき
小牧・長久手の戦いの翌年天正13年春、家康は体がどうもだるい。
一般人が春先になると、けだるくなるというようなそれとはわけが違う。こんなことは今まで無かった。
秀吉対策を練ろうとしても根が続かない。背中がおかしいと思って看させると、腫物ができていた。
つまらないものができたと半ば腹を立てているうちに、それがたちまち成長し、巨大化するにつれ痛みも激しくなる。
はまぐりの貝ではさんで膿を絞らせた。こじれたのかよけい根を大きくさせたようである。
痛みで意識がもうろうとなる。疲れきってウトウトしたかと思うと、とたんに激痛におそわれ、もうろうとしながら意識の世界へ引き戻される。
手の施しようも無く5日ほどたつうちに、すっかり衰えてしまった。体力の衰弱だけでなく、気力が無くなった。
小牧・長久手で、家康は秀吉の実力を直接知った。あれからというもの、武田信玄からうけた圧迫感にはおよばなかったが、「戦闘で勝って戦略で負けた」という思いがのしかかっていた。
(中略)
その精神のすきまを強烈な細菌が襲った感じで、あまりの痛さが、あの我慢強い家康という人間を変えた。
重臣たちが枕元に呼び集められた。
「わしは、もうだめだ。秀吉めは、着々と計画を進めるだろう。よく聞け。」
遺言である。まさか、と思い、しかし誰も分別がつかず、家康の口元をみいるだけであった。
「第一は、おまえ達がまとまって、崩れないことだ。第二は、北条を・・・・」
その時、「殿!、何を申されます。」と、大喝した者がいた。本多作左衛門重次である。
「わたくしも大変な腫物で苦しみましたが、糟屋長閑の治療で全快しました。ぜひ長閑をお召しください。治ります。あやつは治します。」
家康は医者が大嫌いだった。
「いや寿命だ。寿命だからしかたがない。わしにはそれがわかる。まず、わしの言うことを聞け。」
「いえ、ともかく一度手当てを−」
「いらぬ。」
「・・・・・・・」
重次は、口を家康の耳に押し付けるようにした。
「ききわけの無いお人だ。ならば、しかたありません。重なる合戦で、片目はつぶれ、指がもげ、びっこになりました。わたくしのような老いぼれはあとに残っても役に立ちません。一足先に行って、冥途の道掃除でもしていましょう。ごめん。」
この重次のことばで、家康は、戦場で死に、傷ついた者の痛みをふと感じ、自分を取り戻した。気力をなくしてしまったことが不思議なほどであったが、ここでそれを瞬間的に取り戻したことも、奇跡のようなものだった。
重次のことばを受止めたものは、やはり家康の根っからの、戦国武将の血であったのだろう。遺言を言うところまで追いつめられたと思い、ところが遺言はまだ具体的内容をもつまでに整ってなどいない。
団結しろ、背後の北条を敵にまわすなくらいは誰でも言う。その様な曖昧さの中に自分がいたことに、家康は驚いた。それを、重次の別な痛みが知覚させてくれた。
(わしに対策が立たなくて、他の者がどうして徳川を支えられるか。わしがいて、作左衛門のような家来がいて、はじめて可能ではないか。治療がたとえ効かなくてもやってみなくてはだめだ。)ついさっきまでの弱気が、うそのように思えた。
「長閑を呼べ。作左、もうよい。」
糟屋長閑の治療で家康は治った。本多重次がいなければ、家康はこの時死んでいた。
「小説
信長 秀吉 家康」より
新編
藩翰譜における同記述にリンク
▲ページトップへ戻る
|