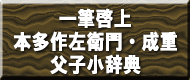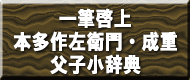「新編 藩翰譜」(新井白石著 元禄十四年呈上)における
本多重次・成重父子についての記述
漢字、かな使いは原文のまま
本多
飛騨守藤原成重(なりしげ)は、作左衛門重次(しげつぐ)が子。本多右馬助助定が後胤、三河国徳川家譜代相伝の御家人なり。
作左衛門重次、生年七歳にて贈大納言家に仕へまいらせしより徳川殿の御時に至りて、度度の高名数を知らず。
永禄八年、三河国尽く御手に属しけれは、此の年三月七日始めて奉行職を置かれて、本多作左衛門重次、高力(こうりき)与左衛門清長、天野三郎兵衛康景(やすかげ)三人に仰せて、其の職を掌らしめらる。
| 此の時三河国にて、歌に、仏(ほとけ)高力、鬼作左、どちへんなしの天野三郎兵衛と謡ふ。
重次はおそろしけなる男の、おのが云ひたき事をばありのままにうちいひ、如何にも思慮あるべき人とも見えず、かかる職務に堪ふべき者にあらずと見えしに、心正しく直く、しかも民を使ふに康ありて、訟を聞きわかつ事明らかなりしかは、人みな徳川殿の御計ひを感じまいらせしとなり。
|
元亀三年の冬、三方が原の戦に重次馬射られて落ちたり。敵十騎が中に取りとめられ、鎗取りのべて敵一騎つき落とし、首かき切り、其の馬取って打乗り、浜松の城に馳せ帰りて見参す。徳川殿、敵進みて我が城を攻めんに、御方多勢ならむには兵糧また続ぐべからず、比の事如何にと仰せあり。重次承りて、信玄我が国に向かふと聞えしより、糧米多く蓄へ積ませて候と答え申しければ、悦びたまふ事斜ならず。比の後は、ここかしこ軍だちし玉ふ時、多くは其の後に留まり守る。
同じき八年三月、長沢の城落ちし時、重次、内藤三左衛門信成と共にしばし比の城を守り、十二年掛川の城を攻められしにー方の大将を承り、城おちて後、酒井、石川等と同じく守る。
天正元年の秋、長篠の城を攻めらる。武田四郎勝頼うしろ巻せんとて軍勢二手に引きわけて、三河、遠江に打ち出る。重次、此の時は榊原大須賀と浜松の城に留まりしが、重次、我等が留守の料に、いざ間近き武田刑部入道信綱(道遥軒と号す)が陣打破って捨てなば、残る敵は戦はずして破れんずとて、三手の勢を合はせて、九月十日、信綱が陣取つたる森の里に押寄せ散散に打破り、重次人々に向かって、信綱負けぬと聞かば、ここかしこの敵、一定助けにや来るべき、勝って冑の緒をしむるという事の候ぞや、いざ帰らんとて引きかへす。案の如く穴山、一条、山県などいう宗徒の者共、鞭鐙を合はせて馳せ来れども、御方既に引返し、長篠また落ちけれは皆本国に引返す(武田家の古兵共、当家まけ軍の始めなりとて、皆眉を顰めしといふ)。
同三年長篠の合戦に、大勢の中に切って入り、能き敵と引組んで落ち重なりて首をとり、敵八人が中に取りこめられ八方に切ってまはる。敵は八人、身は独り、七か所まで手は負ひつ、既に危く見えし所に郎等一人おち合ひて、二人を切って捨つ。残る敵を追払ひ辛さ命は生きてけり。
同じき四年六月十一日、寄騎の士百騎、重次が手に属せらる。
同じき七年八月、三郎殿の御事ありて後、重次仰せを承り岡崎の城を守る。高天神の城落ちし時、重次が手に打ちとる首十八、十余人を生補りす。
同じき十年の春、武田亡び、同じき夏、織田殿うたれ玉ひ、甲斐、信濃再び乱れしかは、徳川殿、彼の国に向かひ玉ふ。北条も同じく彼国々争ひ玉ふと聞えしかば、其の勢を引きわけて駿河国にや攻め入らんと、重次沼津の城を守る(一説に、重次は江尻にあり、沼津をば松平周防守康親守れりといふ。審かならず)。案の如く、九月廿五日、北条の軍勢、韮山の城より打って出て戸倉山に至る。重次逆寄にして打破り、韮山の城戸口まで追ひ詰めて、首三十余を切って引返す。
同じき十二年小牧に陣し玉ふ時、重次、伊勢の国星崎の城を守る。蟹江の城を攻められしに、先陣して城を攻めおとす。
頓て秀吉、信雄、中直りし玉ひ、信雄に就きて於義丸殿を養君とし玉ふ時、重次が子仙千代丸も、石川伯耆守数正が子と同じく附けて参らす。抑(そもそも)此の於義丸殿と申すは徳川殿の御二男。故ありて生れ落ちさせ玉ひしより、重次とりて養ひ参らす。此の年御とし十一になり玉ふが、都に登らせ玉ふ事を御名残をしく思ひしかは、我が独子にて愛しける仙千代丸つけてまいらせたり。
秀吉も、うへには於義丸殿を養ひ参らするとは披露あれど、内々は人質とし、徳川殿に親しくならん謀にてありければ、本多は殊に彼家譜代のおとななり。其の子を参らせし事こそ嬉しけれと悦び玉ふ事斜ならず。
去る程に、秀吉、正二位内大臣に歴上り、関白の職になって、於義丸殿にも元服させ、秀康と名乗らせ、従四位下左少将兼参河守に任じ、信雄卿を媒とし、徳川殿御上洛の事を勧め玉ふこと度度に及べども、上り玉ふべしとも聞えず。依りて三河守殿も失はれさせ給ふべしなど風聞す。
三河守殿の御母、此の事を聞き玉ひ、守殿失はれ給ひて後、一日も世にながらふべしとも覚えず、死なばー所にこそ死なめとて忍びて大坂に上らせ玉ふ。
重次、いやいや仙千代丸、都に置きて人の疑ひ受けん事も詮なし、ただ独りある子失はれんも不便なりと思ひけれは、母がいたはり以ての外に候、暫しの暇を給ひて此の世の暇乞をも仕らせばやと、守殿へ申して呼び迎へぬ。
幾程なく、石川伯耆守数正は徳川殿に背きて、秀吉の御方に参る。扨こそ重次がニ心なき所顕はれて誠に思慮深くは見えけれ。斯て関白殿の仰せにて、仙千代丸とく参らすべしと守殿よりの御使度々に及ぶ。
重次も詮かたなく、是もいたはる所の侯、且は母が病も、年頃この子恋ひ纂ひし故なれば、今更参らすべしとも覚えずと伏し沈み歎きぬ。
されば息男が身代りの此の者参らするとて甥の源四郎富正を参らす。関白殿、安からぬ事なり、本多めにたばかられたりけりと怒りたまふ事大方ならず。
かかりし程に、また東西の軍起こりなんと聞えて、宗徒の御家人の中、岡崎の城守るべきものを選ばる。本多佐渡守正信承りて、此の城を枕として討死仕るべき者に仰せ付けらるべしと申しければ、やがて重次召して岡崎の城を給はり、数百騎の兵を属けらる。
| 此時、重次が御暇乞申しし気色、生きて再び見参すべしとも見えざれは、其の志を感じさせ給ひて、息男成重、本額安堵の御書を成し下さる。其の御書に、天正十三年十二月八日としるされ、本多丹下殿となされけるとなり。 |
関白殿、いかにもして徳川殿と親しうならんといろいろに謀をめぐらし、頓てまた其の妹君を徳川殿の北の方に参らせられしかは、徳川殿、此の上は見参なくては叶ふまじとて御上洛あるべきに極る。
御家人等が危く思はん所も侍る故、都に御逗留あらん程はそれに留めさせ玉ふべしとて大庁(おおまんどころ)を下し給ひしかば、岡崎の城に入れまいらせ、重次これを守る。井伊(直政)、大久保(忠世)も同じく御後にとどまる。
| 此の時重次下知して、大庁のおはしますほとりに、薪を積むこと山の如し。
こはそも如何なる事ぞと驚き、大政所の御供せし女房たち、はした女して薪つむ下部男一人まねき、酒など呑ませ、心能くとりて、扨(さて)何事にか、この程日々にかく薪をは積むさぞと間へば、いかなる事とも下郎は如何で知り申さじ、ただし承る所は、関白殿の我が国の殿を失ひ玉ふか、若しくは留めまいらせて返し玉はずは、今度部より御下り有りて是にまします御方を、尽く焼殺し申さん料の薪とかや申して、本多殿の下知として日々に山林より切って来り候が、この本多殿と申すは、極めて気の短き人にて、殿の御帰り、おそしおそしと待ちかねて、けさ火を附けう、晩に焼きたてうとせられ候を、井伊殿や大久保殿がしはししばしと制し玉へはこそ今迄はかくて候へ、痛はしや美しき都上らふの、今のうちにも灰土にならせ玉はん事の無慙さよと下郎等は申す事にて候と云ひしを、女房達に斯といへは、あな悲しや、その本多といふ男が日々に参りて、おそろしげなるこわねにて、家康よりげんにつけて参らせて候、御用の事あらは承りなんずといふを今思ひ合はすれば、三河守殿(秀康)の初めて御参ありし時、仙千代丸といふ児の御供したるを殿下の御覧じて、あれは家康がうちにて三奉行とか云ふうちの鬼作左衛門と云うものゝ子ぞと仰せありしかば、おそろしおそろし、鬼も子を生むにや、鬼の子は如何なる者にやとて物越に人々の見たりしに、其の親の鬼ならば、さてこそはあらめ、さればこそこれへ参る度毎に、家康返り候はんとの事は、いまだ御沙汰も聞え候はぬやと、おととひもいひしぞ、けさも、きのふもいひしぞ、待ち遠にや思ふらん、あはれ家康とくしてかへさせ玉へかしとなきくどきて、此の由を大庁へ申けれは、大いに驚き、なげき玉ひて、日々に御消息ありて、徳川殿をとくかへさせ給へ、こなたのありさまのいぶせき、いつの世にかは忘るべきなど、ありし事共こまごまと仰せ遣はされし程に、ほどなく御帰国ましまし、大庁帰りのぼらせ玉ひければ、女房たち涙を流し、なさけなくも御母上を下したまひしものかな、鬼本多とかやが、かくこそいふたれとこそ計らうてさむらひつれ、今は朝日の姫君をまいらせ玉へは、徳川殿の御ためにも大庁は御母上にて候ふを、如何に鬼なればとて己が主の事しらぬ事や候べき、それにかく辛き目を見せ参らせて侍れは、はやはや徳川殿に仰せられて如何なる罪にもあはせて、大庁の御恨みをも晴させ玉へととりどりに訴えければ、関白殿笑はせ玉ひて、家康はよき者共あまた召し仕ひけり、秀吉もその如き家人をばほしき事に候ふぞや、とばかり宣ひて、御座をたたせたまひしとなり。
作左衛門エピソードへリンク
|
同じき十八年正月、関白殿、北条を追討の事ありて、我が国々を打ちて下り給ふべし、御陣のために海道の城々を借しまいらすべしとて重次と佐波守正信とに奉行せさせ、修理の事仰せ下さる。
同じき三月、関白殿岡崎の城に入り玉ふ。此の城は重次守る所なれど、御迎へにも参らず、城へ入らせ玉ひし後も見参にも及はず、関白殿より加藤遠江守を御使にて、三度まで召しけれども、重次は関白殿に見参して申すべき用もなし、御免あらんとて終に参らず。
| 一説に、同じき廿日、関白殿、駿河の国府の城に入りたまふ時、徳川殿、長久保の御陣より参り玉ひ、御対面の儀ありて、重次此の所に参りて、関白殿、御家人あまた居並びたる所にて、徳川殿の御後より参りて立はだかり、大いに声をいからかして、やあ殿よ殿、あっぱれ不思議を振舞ひ玉ふよ、国をも保たんずる人が我が城を打明けて、暫しも人に借す事やある、その気にては人の借らんといはんには、一定北の方をも借し玉はんするよなど罵り罵り立帰る。
徳川殿、人々に打向かひ玉ひ、今の老人が申したるやうを聞きたまひてこそ候らめ、あの老人と申すは本多作左衛門重次とて家康が累代の家人、家康が幼なきより仕へぬ、年若
きうちより弓矢、うち物取っては人にも知られ候ひしが、今は見たまひし様に年もいたう寄りて候、されば家康も不便のものに存すといへども、天性我儘なる根性にて、人をばはふ虫とも思はず、人々の聞き玉ふ所にてだに家康をかく事かましう申す、まして只二人うち向かうたる時の事思ひやり給ふべし、常には如何にも候ひなん、いかでけふもかかる奇径をばふるまふべき、人々の思ひ給はん所、耻しう候と仰せけれは、在りあふ人々一向に、此の人の事久しく承り及ぶといへども、見及びしは今こそ始めなれ、誠に聞きしにまさりて候ものかな、事新しうは候へども、かかる卸家人の候事、奥ゆかしう覚えて候と色代せしと云ふ。
按ずるに重次、此の度海道の城に修理の奉行たり。此の城借し玉ふ事いかで知らざるべき。然るにかく京家の人々の集りし所にして、思ふやうに云ひちらしたる事、誠にさる智ふかき人なり。重次にあらずしては及ぶまじ。されば此の説あやまるべからざるにや(小田原へは重次二の先にてむかひしといふ説あり)。
作左衛門エピソードへリンク
|
程なく北条亡び、関東を以て徳川殿知行有るべしと定められし時、関白殿、むかし本多が秀吉をたばかつておのが子を取返し、此の度また秀吉が下向の時、対面すべもよし使者を以て言葉をつくせども、終に参らず、彼といひ、是といひ、其の科(とが)軽からず、かかる者召仕はれん事、然るべからずと大いに怒り仰せけれは、彼が怒り散ぜん程は籠り居よかしと思召しけれは、上総国北原の庄にて、老養ふべき程の所頭(三千石)給ひて、忍び忍びに御使ありて、常には間はせ玉ひしが、程なく彼所にて終りけるこそ哀れなれ(一説に、慶長五年関が原合戦の頃迄存命にて、その時には江戸の留守たりしと云ふ。覚束なし)。
| 去りし天正三年三月に、徳川殿御脊中に疔といふもの出来て、既に危く見えさせ給ひしかば、内外の医、療術を尽しけれどもそのしるしなく、唯弱りに弱らせ玉ひ、みづからもこれまでと思召しけるにや、宗徒の御家人等めし集めて御跡の事ども仰せおかる。
人々の周章いふに及はず、士民、百姓等に至るまで、その程々に従ひて祈らぬ神仏もなく、立てぬ願もなし。
重次、御枕に取りつきて泣く泣く申しけるは、殿も定めて覚えさせ玉ひなん、重次がむかし此の病をうけしに、たち所にしるし得し良医の候、彼を召して見せ試み玉ふべしと申す。
諸医既に手をつかね、家康また死を決す、この上医療其の詮なし、且は命をしむに似たりとて用い玉はず。
重次大いに怒りて、かほど大事の腫物、かろがるしく思召し侮つて、事急なるに臨めばこそ諸医も術尽きぬれ、夫にまた良医して治しまいらせんとするをも用い玉はず、失せ玉はん事、御心がらとは云ひながら、あつたらしき命かな、諸医、術尽きぬと申す上は彼等いかでか治しまいらすべき、年老いたる重次が、御跡にさがつての御供かなふべからず、さらば御先へ参らん、とて御前を罷り立つ。
徳川殿大いに驚かせたまひ、あれ止めよと仰せければ、近く侍らふ人々走り出で引きとどめ、仰らるべき旨あらせられ候といふ。
重次、大いに声を怒らして、最期の暇乞ひてまかり申す者を、見苦しい殿原の止めやうやと罵って出でんとす。
されは候、その人を止めよとの御使が、えこそ止めねと申せとは、おとなしくも侯はぬ本多殿と云はれて、げにはさも候、とて御前にまいる。
徳川殿、汝は物に狂ひてかくは云ふか、家康いまだ死しはてぬに、たとひ家康が命終るとも、汝が世にあらんを頼みにこそ死すべけれ、又汝等も如何にもしてー日も世に残りて、若き者ども掟して、我が家の絶えざらん様を計らんとは思はずして、詮なき死の供せんとする事やある、と仰せければ、いやいや、夫は人に依っての事に候、重次も今少し年だに若く候はんには、仰せ迄も候はず、犬死せん人の御供、其詮なし、重次若年の昔よりここかしこの軍に従ひて、眼射られ、指落され、足切られて、負はぬ手も侯はず、人のかたはといふ程のかたは、重次が身ひとつに余って、世に交らん事叶ふべき身ならず、殿の御情ふかけれはこそ当家にては人に恐れも恭はれも仕つれ、殿のなくならせ給ひなば、他人までも候まじ、先つ御聟の北条殿、我が国々を取らんとし玉はんに、わかき人々が行くすえ久しう仕へんと頼みきったる主に、忽ちに別れて、気おくれし、はかばかしき矢のー筋をも射出す事かなふべからす、当家亡されん事また踵をめぐらすべからず、重次夫迄ながらへて、あの年寄つたるかたは者は、徳川殿の譜代にて何かしといはれし家人なるが、いかに借しき命なればかく世には耻をさらすらんとうしろ指さされん事、老の耻、何事かこれにすぎ候ふべき、此比までも、武功の家の人々御当家に召されて、さらぬ人にも手をつかね、膝を屈めしを、世にもあはれに思ひしが、今は此の老人めが身の上になって候と存ずれは、殿におくれ参らせんが悲しき計にも候はず、我が身の果もあさましさに因て御先に死する事にて候と申す。
汝がいふ所ことわり至極せり、さらば医療の事は汝が心にまかすべし、天命既に至りて家康空しくならんとも、汝もまた家康が心に任せ、ぃかなる耻を見つべしとも、一日も生き残りて、後の事よさに計らふべしと存ずるや、いなやと仰せけれは、重次が申すむねに任せられんには、重次いかで又仰せをや背くべきと申す。
さらば医師めさせよとて召さる。医師やがて参りて、御灸治よろしかるべしと申せば、重次艾(もぐさ)とってすうる。
御灸の痛み覚えさせ給はねば、艾を増し加ふる事多くして、後いささか痛ませたまふよし仰せけれは、御薬湯をも進め奉りしに、其の夜の半ば
に御腫物潰れて濃水血おひただしう流れ出て、御悩み立ち所に軽ませ玉へば、重次は嬉し泣きに声をかぎりに泣く。
御前伺候の人々も御涙を共に流しけり。此の人かかる奉公の事ども、世に伝ふること多し。尽く記るすに暇あらず。大畧をしるすのみ。
作左衛門エピソードへリンク
|
其の子は飛騨守成重なり。童名は仙千代丸、成人して丹下と申し、相川小田原の御陣に、重次、成重後陣に在り。重次、籠居せし後は、成重も出仕を止めて籠り居ぬ。関が原の合戦には御後にぞ陣しける。
慶長十八年、越前国丸岡の地を賜ひて、少将忠直朝臣(秀康の子)の家にぞ附けられける(創業記に、慶長十八年、越前の家老今村掃部介、清水丹後守、相論の事ありて二人共に配流せらる。越前の福井をば、本多伊豆守に仰せ下され、今まで今村が領せし丸岡の城をば、本多丹下に玉ふと云云。四万三干三百右余を領せしなり。
一説に、慶長六年に結城殿に附けらるといふ、覚束はし。
また伊豆守といふは、むかし成重が身代りに都へのぼりし、源四郎富正と申ししが事なり)。
大坂前後の戦に越前の先陣し、前年十二月四日、御方の先陣、城を攻めし時、成重郎徒討たるるもの十六騎、疵蒙るもの百六十人。
後年五月七日、成重が三百騎真先に進み、真田左衛門尉幸村が陣を打破り、みづから敵二騎切っておとし、郎徒等が切る所の首百七十三。城門を打破りてー番に城に入り、ここかしこに火を懸け、首二十八を切る。手の者討たれしもの五人、疵蒙れるもの七人。
元和九年、忠直朝臣配流の後、再ぴ将軍家の御家人となりたるなり。年老いて子息淡略守重能に家譲り、入道して土庵と号す(成重が致仕せし年、卒せし年、いまだ知らず)。
淡路守重能、慶安四年十二月七日卒す、六十二歳なり。
其の子飛騨守重昭(しげあき)父に継ぐ。延宝四年正月十五日に卒す。
其の子作左衛門重益(しげます)、家を継ぎて飛騨守に任ず。